【ネタバレあり・レビュー】砂漠の鬼将軍 | アメリカが描く実在したドイツ軍人エルヴィン・ロンメルの物語
第二次世界大戦時のナチス・ドイツといえば悪党というイメージしかありません。
しかし、それは独裁者アドルフ・ヒトラーの行き過ぎた思想があったがため。
ドイツ軍人皆がヒトラーのような過激思想を持っていたわけではありません。
そんなヒトラーの考え方に疑問を抱き、ドイツを救うために戦った一人の軍人エルヴィン・ロンメルの物語を追った作品が『砂漠の鬼将軍』です。
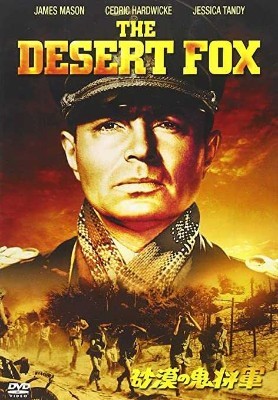
ストーリー
第2次世界大戦下のアフリカ戦線。最前線で指揮を執るドイツ軍のロンメル将軍は、最前線の過酷な状況を顧みない上層部の判断に不満を募らせていた。
やがてその怒りは、ロンメル将軍をヒトラー総統の暗殺計画に向かわせる。
感想
『砂漠の鬼将軍』なんていうタイトルが付いているだけに、ロンメル元帥は超スパルタでパワハラ上司をイメージしていました。しかし、実際見てみれば彼は戦場を客観的に見ており、無駄な犠牲者を出そうとしない穏健派。
これまでナチスに抱いていた悪いイメージすら覆しかねないような人格者であることが感じ取れました。
そんなロンメル元帥を追った作品なのですが、物語は彼の謎の死を英国兵士のデズモンド・ヤングが追うことからはじまります。
彼が得た情報から、断片的にロンメル元帥の動向を描いていたのはなかなかに効果的。
ロンメル元帥がナチス軍へ不信感を抱き、やがては反逆を企てるまでに至る思想を分かりやすくまとめていたと思います。
余談なのですが、このデズモンド・ヤングという方はロンメル元帥同様に実在した人物です。
彼の描いた手記が本作の原作ともなっており、作品を語る上では欠かせない人物だと言えます。
それを本人自身が演じたというのが、また面白い話。
本作が製作されたのが、第二次世界大戦からそれほど時が経っていないということを感じさせました。
「ロンメル元帥がナチス軍へ不信感を抱き、やがては反逆を企てる」とざっくり書きましたが、作中ではこの中の「不信感を抱くまで」が全体の8割くらいを占めていたと思います。
そこから見えてくるのは、ナチスを率いるアドルフ・ヒトラーの過激な思想でした。
彼はまさにイメージ通りの悪党。必ず負けると自他ともに認めていようとも「勝利か死か」を提唱し続けて絶対に撤退を許しません。
前線のロンメル元帥がどれだけ苦言を呈しようとも聞き入れない頑固さっぷりはまさに独裁者です。
ロンメル元帥がフラストレーションを溜めていき、やがて反逆に足を踏み入れてしまうというのも納得の傲慢さを見せていました。
それだけに、ナチスの在り方に疑問を抱き、信念を曲げずに立ち向かったロンメル元帥の姿は尊敬に値するものでした。
もちろんそれは口先だけではなく、命令に背いてでも撤退を試みたり、上層部に直談判をしたりと、行動でも表していました。
最後にはヒトラーの下へ直接出向いてナチスの降伏を進言。
銃殺刑すら考えられる緊迫の状況下で、一歩も引かない意志の強さは本当の意味でドイツを想っていることが感じられました。
こうしたロンメル元帥の軍人としての素晴らしさを描いていた本作。
しかし、その一方で普通の家庭を持つ夫であり、父であることを描いていたのも印象的でした。
中でも妻との関係は素敵です。
ヒトラーに対する不信感を抱いている秘密を共有し、常に味方であり続ける献身ぶりはロンメル元帥を支えていたと言えます。
彼が死を覚悟していることを知っても決して取り乱さない器量を持ち合わせており、最後の別れをいつものように見送るシーンは感動的でした。
ロンメル元帥の裏に、妻の支えありというのが伝わってきました。
このように、ロンメル元帥に対するリスペクトがあらゆる箇所で見られたわけですが、面白いのがこの作品は戦後間もない1951年にアメリカが制作したということです。
アメリカといえばご存じの通りナチス・ドイツ軍とは敵対関係にありました。
にも関わらず、ドイツ軍人の尊さを称えるような内容の作品を作っていたんですね。
ラストシーンには、ウィンストン・チャーチルが彼を「騎士道精神の宿る貴重な男だった」と称する声も入れられており、公開当時にどのような扱いであったのかが気になりました。
他にも、明らかに実写の戦争シーンが間に挟まれていたりと、今の時代では見られない(CGで済ませてしまう)ような映像もあってある意味新鮮でした。
これぞ古きよき戦争映画と言えるでしょう。
ナチス・ドイツ軍の中でも本当の意味で国や兵のことを考えていたロンメル元帥。
その人間性の素晴らしさを、ヒトラーの有無を言わせぬ命令によって苦しめられる兵士を通して描いていたのが痛烈に刺さる内容でした。
救いのない話ではあるものの、エルヴィン・ロンメルが何を見て、何を思ったのかを知ることのできる名作と呼ぶべき作品であったと言えるでしょう。